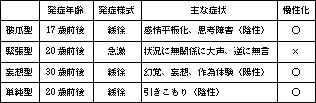特徴
€ 内因性精神病:何らかの遺伝素質などを推定した言葉
主として青年期に発病:多くは、15歳から30歳までに発病し、特に20歳前後に好発
¡ しばしま慢性進行性に経過:段階的に増悪を繰り返すことが多く、予後はあまり良くない
¤ 末期に特有の残遺状態(欠陥状態)を残す可能性:社会的な存在として不可欠な共感性、 活力、興味関心などを失い、自己の世界に閉じこもり、環境との接触を断った特有の状態
¦ 出現頻度(発生率)は、0.7%前後
|
原因 |
・不明(陽性症状では中脳−辺縁系ドパミン作動性神経路の過敏状態が基盤) |
|
症状 |
急性期(陽性症状)---
抗精神病薬の反応良好 |
|
治療法 |
・抗精神病薬(ハロペリドール、クロルプロマジンなどのメジャートランキライザー)による薬物療法が必須。 |
精神分裂病の症状
|
客観的な症状 |
主観的な症状 |
|
1)動作や表情の異常 |
1)妄想 |
抗精神病薬の副作用
|
1.自律神経系への副作用: |
抗精神病薬
|
一般名 |
商品名 |
特徴・その他 |
|
I. フェノチアジン系誘導体 |
|
|
|
II.ブチロフェノン誘導体 |
|
|
|
III.チオキサンテン誘導体 |
|
ハ |
|
IV.レセルピン |
|
|
|
V.インドール誘導体 |
|
|
|
その他 |
|
|