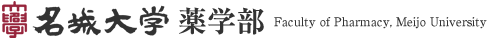藤田保健衛生大学病院における臨床研修レポート
Olivier MAURION
フランス、ナンシー大学薬学部5年
まず最初に、私が、日本の病院でどのように医療が行われているかや名城大学の大学院生の臨床研修がどのように行われているかを学ぶことをお許し頂いた名城大学の皆様に感謝申し上げます。
この一ヶ月半の間、私は多くのことを学びました。病棟では、それぞれ異なった疾患や疾患に関わる検査を見学することができました。それは非常に興味深いものでした。さらに、日本の大学院生の研修はフランスの薬学生のそれと比較して全く異なっています。この研修期間に私が目を見張った診療のプロセスや組織についてこのレポートで説明していこうと思います。しかし、私が実際にフランスで研修していたOncologyセンターは、藤田大学病院とは異なり病床数などの規模が小さい病院であったことから、一概に日本とフランスの病院を比較することもできませんが。
私は名古屋市の南西部に位置する藤田保健衛生大学病院で、臨床研修を行いました。本院は、ベッド数が1510床、1日平均の外来患者数が約2500人であり、日本で3番目に大きい病院です。
私の研修は3~4日のローテーションでいくつかの診療科を訪問し、各診療科で研修している大学院生と共に研修を行いました。
私が最初に研修を行った病棟は消化器内科でした。この病棟は私にとって最初に研修を始める上で良い病棟でした。私はこの病棟で本院の病棟の体制を学び、X線検査や内視鏡などの多くのことを見学できました。また、この病棟では大学院生の安田玲子さんと共に研修し、彼女はこの病棟のすべての医師と教授を私に紹介してくれました。医師たちからこの病棟や肝臓癌や胃癌などの疾患について話を聞くことができました。
また、私はこの病棟では、2~3ヶ月前から導入された患者情報の電子ファイルを知ることができました。この病院では、患者情報はすべて電子化されており、すべての医療スタッフが末端のコンピュータにより患者データを閲覧できます。コンピュータにすべてのデータを入力するには時間がかかることやこのシステムの導入には費用がかかることなどの欠点はありますが、このシステムは非常に良いものであると思います。
2番目に、大学院生の福井愛子さんと共にGeneral Intensive Care Unit(GICU)にて研修を行いました。GICUは、藤田保健衛生大学病院の救急救命センターです。フランスでは実際に見学することは難しいことから、このGICUを見学することができて嬉しかったです。このGICUではベッド数が37床あり、その内Cardiology Care Unitが10床、Surgery Care Unitが14床あります。
2日間で、心臓発作、交通事故、インシュリンによる自殺者、脳卒中などのさまざまな急患を見ることができました。救急救命センターの荒木教授が各患者について、名前、年齢、性別、意識レベル、体温や血圧などの患者データをシートに記録します。この日本おける救急システムはフランスとは異なっています。フランスでは、多くの人が自分自身で救急救命室に来ます。しかし、日本では、急患だけが救急救命室に入ります。さらに、患者データを追跡するためや、予測される薬物の副作用や治療効果を見るために適正なモニタリングを行うことの必要性を認識しました。このGICUは特別な病棟であり、この病棟では薬剤師は、おそらく患者の薬物中毒となった薬物の特性を確認することですが、私にとっては非常に興味深いものでした。
3番目に、大学院生の寺澤知彦君と杉山絵美さんと共に呼吸器内科にて研修を行いました。この病棟で、私が見た主な疾患は肺癌です。また、私は病棟のシステムと構造についてもさらに学ぶことができました。私は患者の部屋の中にトイレや浴室がないことに驚きました。また、重症な患者は個室に入ることもわかりました。私は外来患者のために薬物を調整する化学療法室を見ることができました。私はフランスではOncologyセンターにて研修を行ったことから、この部屋とフランスの化学療法室と比較することができます。この部屋はフランスの病院と同様ですが、唯一、無菌室でないことが大きな違いです。また、ここでは、フランスのように調剤助手(テクニシャン)ではなく、薬剤師が自ら薬を調製していました。また、日本ではモルヒネがそれほど使用されていないのに気付きました。例えば、日本では実際にモルヒネポンプを使用しませんが(見学の期間中に)、フランスでは、よくそれを癌患者に使用しています。この病棟では、多くの癌患者と接触することができました。日本ではどのように化学療法剤が調製されているかを知ることもでき、興味深いものでした。
4番目は、矢田裕美子と早川英子さんと共に代謝・内分泌にて研修を行いました。この病棟では、患者の多くは2型糖尿病でした。患者は自身で血糖値を測定します。例えば、Basedow病のような代謝性疾患を伴った患者が多くいます。ここでは、私は、病院薬剤師が糖尿病患者を対象として糖尿病の合併症についての説明を行っているところ(病院薬剤師による糖尿病教室)を見ました。フランスの病院薬剤師はこのようなことは行っていない(薬局薬剤師は行っていますが)と思いますので、この薬剤師の業務は良いことだと思います。
私は鈴木教授のご教授に厚く感謝致します。鈴木教授は症例について英語あるいはフランス語で私に丁寧に解説していただきました。
また、私は、日本の病院では、医師が患者が入院する前にどれくらいの期間、入院するかを知っていることを知りました。例えば、糖尿病患者に関しては、2週間、入院するでしょう。このシステムは、米国のように入院の医療費を下げるために適しています。日本では、糖尿病はますます増加しつつあります。それは、明らかに以前と異なった栄養摂取が原因となっています。日本人は何年も前にはあまり甘い食物を摂取していなかったことから、コレステロールや糖尿病の問題はありませんでした。しかし、現在は、米国式の食物の摂取とともに、油っこい食物や砂糖の摂取の増加が原因で、日本ではますます多くの糖尿病患者が増えているようです。グルカゴンの分泌量が減少するとインスリン分泌量は増加する。私は、この病棟に患者が入院する時、大学院生が患者の既往歴、喫煙歴、飲酒歴や入院前に使用していた薬などについて患者インタビューを行っているところを見学しました。私はこのように薬剤師が患者との会話の仕方を知ることは大変良いことであると思います。
5番目は、大学院生の廣瀬正幸君と共に一般内科にて研修を行いました。この病棟では、多くの疾患、特に吐き気、けいれん、リンパ腫、好中球減少などを伴った患者(約20~30名)を見ることができました。
6番目は、大学院生の中島有佳子さんと共に循環器内科にて研修を行いました。この病棟では、約60人の患者と10床のCardiology Care Unitがあります。私が見た患者の多くは、心不全と心筋梗塞です。日本ではフランスと同様に、-遮断薬、ACE阻害薬,スタチン類、利尿薬などの多くの種類の薬が使われます。Cardiology Care Unitではすべての患者を見るために、また、十分にモニタリングするために医師や看護師のスタッフが配置されています。さらに、私は、日本の医師がどのように中心栄養静脈のチューブを入れるかを見ることができました。また、冠血管造影を行っている部門の見学では、この検査について多くのことを学びました。皿井医師のご助力に大いに感謝致します。
7番目は、大学院生の中村絵里香さんと共に消化器外科にて研修を行いました。この病棟には約30名の患者がおり、その多くは、すい臓癌、胆嚢癌、胆石やヘルニアでした。用いられている主な薬剤は、gemcitabine、5-FU それに cisplatinです。この病棟は他の病棟と異なり、多くの患者は手術室から運ばれた術後患者です。主な問題は術後の瘢痕形成(傷の治癒)をサポートすることです。患者がこの病棟に入る前には、看護師だけでなく薬剤師や医師によって患者面談記録用紙に多くの情報が記録されます。ここでの研修の最後の日に、男性患者において胆嚢に局在している腫瘍のすばらしい摘出手術を見ることができました。
最後に、大学院生の市川和彦君と共に血液・化学療法科(白血病やリンパ腫など)にて研修を行いました。ここでは、フランスと日本の医療システムが非常に類似していることを理解しました。例えば、Acute Myeloid Leukemia(急性骨髄性白血病)の治療にはanthracycline (daunorubicin、idarubicinなど)とAra-Cが用いることなどは、非常に類似しています。また、CHOPやMACOP-Bのレジメはフランスでもよく使用されています。しかし、aclarubicinなどの日本の薬のいくつかはフランスでは使われていません。また。フランスの薬剤のいくつかは日本にはありません。さらに、私は化学療法薬の混注業務を見ることができました。水田医師に感謝します。
結論として、私は藤田保健衛生大学病院のような日本の大病院において、この研修期間を通じて良い経験をしました。私は日本における大学院生の臨床技能コースは、フランスよりも非常に興味深いものであると思います。その理由は、彼らが患者と面談できること、患者データを診療録から確認することができること、副作用をモニタリングすることができること、それに実際に臨床薬剤師の仕事をできることが挙げられます。しかし、一方では、私はフランスの病院には、特に入院による感染症対策において、より良い組織があると思います。日本の病院はフランスの病院よりも電子的に患者のファイルを所有するという点で近代的であるように思われます。この電子化は医療スタッフにとっても、学生にとっても(データ確認など)非常に便利なものです。さらに、日本の医師は、すべての学生とともに、いつも非常に親切で、親しみやすかった。フランスでは医療スタッフと薬学生との間にはギャップのようなものがあり、時には薬学生が十分な仕事を達成することが難しいことがあります。また、フランスの薬学生と日本の薬学生の臨床研修が異なっている点は、フランスの薬学生は病院の薬剤部と関連した研修を行い、病棟ではなく薬剤部でほとんどの時間を費やす点です。これは、私が、日本の学生がフランスの学生よりも臨床薬学に対してより良いトレーニングを受けていると考える理由です。
私は再び、今回非常に良い経験ができたことを金田薬学部長、平野教授、松葉教授、亀井助教授、大学院生の皆さん、および名城大学の皆様に感謝します。また、日本あるいはフランスでお会いできることを切望します。ありがとうございました。
 藤田保健衛生大学病院で病棟研修を行っているOlivier MAURION 君(中央)と平野教授、大学院生の安田玲子さん。
藤田保健衛生大学病院で病棟研修を行っているOlivier MAURION 君(中央)と平野教授、大学院生の安田玲子さん。
 藤田保健衛生大学医学部のサテライトセミナー室にてフランスの癌専門病院で経験した症例について発表する Olivier MAURION 君
藤田保健衛生大学医学部のサテライトセミナー室にてフランスの癌専門病院で経験した症例について発表する Olivier MAURION 君